
2018年5月、キリストを告白する人口割合がわずか1%である国日本の、12のキリスト教資産が、世界遺産登録に向けて正式に推薦された。
長崎・天草地方にまたがるこれらの資産は、徳川将軍時代(1630-1867)の信者が、アジアの歴史上でも最も厳しい迫害を受け、殉教者を出したことに因む場所である。
資産リストを見ていくと、まず長崎市の大浦天主堂は、日本人クリスチャン17名とヨーロッパ人神父9名が、時の君主の命令により磔(はりつけ)の刑に処されたことを記念する。南島原の原城跡は、カトリック反乱軍が虐殺され、リーダーが打ち首にされ、彼らの信仰が禁止されるに至った一揆の戦場である。その他の「潜伏キリシタン」資産は、キリストに従う者たちが数百年にわたりひそかにその信仰生活を続けたことに因んでいる。
これらの資産は、もし来月、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の認定を受ければ、日本にすでにある14件、全世界では800件余りの世界文化遺産に名を連ねることになる。
日本の推薦は、地元のリーダーがこれらのキリシタン資産について検討申請を提出して以来、5年を経てなされた。日本は5月初旬、諮問機関である国際記念物遺跡会議が、潜伏キリシタン資産を世界遺産一覧に含めることを承認したと知らされた。最終決定は6月下旬のユネスコ会議でなされる見通しだ。
「潜伏キリシタン資産について、日本政府が今回推薦したことは、複数の理由で意味があります」とマコト・フジムラ氏は語る。同氏は、苦難の中での信仰についての自身の著書『Silence and Beauty(邦題 沈黙と美)』の中で、17世紀の日本における迫害を題材とした遠藤周作の小説を扱っている。
「第1に、今回の推薦は、日本国土において潜伏キリシタンの歴史が中心的地位を占めることを認めるものです。[遠藤の]作品「沈黙」は、自国の歴史に関する日本人の理解に対して重要な貢献をしましたが、彼の直感は正しかったと証明するものです。」とフジムラ氏は本紙に語る。「第2に、今回の推薦は、長年の迫害の下でも、キリスト教は目覚ましい回復力を見せたという文化的価値を際立たせるものです。」
世界遺産史跡は、往々にして優れた技工を伴う創造性や、重要な文化的貢献を世に紹介するものだ。それらは国の誇りであり、人気の観光スポットである。ユネスコはまた、特定の伝統の「物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である」場所に認定を与えている。
キリスト教の伝統は、もちろんキリストの復活と、苦難を通しての贖(あがな)いの力という証拠を中心とするものだ。そのような回復力と贖いの力は、日本における教会資産に、痛ましい悲劇の跡として表わされている。
あるカトリックの指導者が述べている通り、「私たちは、自分たちの信仰が最も偉大であった場所を自分たちのものと主張し、世界で最も美しいアートと真の礼拝場所を打ち建てる。」
遠藤の『沈黙』は、2016年にマーティン・スコセッシにより同名の映画となった[訳注:日本では「沈黙−サイレンス」として公開]。この作品では、日本の潜伏キリシタンの間で宣教活動をした、17世紀のポルトガル人神父たちの、他ではあまり知られていない物語を紹介している。権力者たちは、信仰を棄てろ、さもなければ拷問され、殺されると彼らに迫った。仲間のキリシタンたちは「火あぶりにされ、熱湯を浴びせられ、逆さ磔(はりつけ)、打ち首、水責め、浜辺に立てた十字架につけられたまま、満ち潮になぶられる」といった仕打ちを受けた。
極東のローマと呼ばれていた長崎は、教会史上のこの時代に敬意を表する。この街には、キリスト教禁教令が廃止された後に最初に建てられた教会の一つである浦上天主堂がある。また、二十六殉教聖人の記念碑や、今年開館したばかりだが、キリシタン迫害の歴史を専門に扱う博物館もある。
「本当のローマと同じように、ここ長崎、特に浦上は、最も大規模なクリスチャン迫害の地だ。ローマでも、ローマ帝国の大皇帝らが古代教会に残忍な仕打ちをした。」と、日本在住のカトリック著作家でブロガーのショーン・マカーフィーは記している。「ここ浦上で、極東の信仰のキャンドルが灯され、その火は隠されてはいたが、完全に消されることはなかった。」
長崎のその他の場所と同様に、教会も第二次世界大戦中に悪名高い原爆投下の後、廃墟と化した街の中で再建されなければならなかった。長崎は、カトリック教徒の国内巡礼地に指定されている。
日本ではユネスコや新たな博物館を通して、キリスト教の痛ましい歴史に光を当てようという動きが進んでいるが、同じような動向は諸外国でも見られる。教会は過去の悲劇的な、あるいは恥ずべき時代を記念し、そこから学ぼうとしている。
2017年の本紙トップ記事は、米国におけるリンチという遺産に触れ、オープンしたばかりの「平和と正義のための国立記念碑」を、神学者の故ジェームズ・H・コーン氏と内覧するものだった。コーン氏はリンチに使われた木を「キリストの十字架を思い巡らすための現実的な物体またシンボル」としてとらえた。
歴史ある教会は、南軍、奴隷所有者であったリーダー、今日ではもはや承認不可能な考えを持っていたその他の人々との過去のつながりを、認めるべきかどうか、またどう認識するべきか、考えあぐねてきた。それは本紙が昨年、以下のように報じたとおりだ。
史跡は、記念すべき遺産だとして擁護する人もいれば、過去の罪を告白するための一つの手段としてとらえる人もいる。ドイツのラビたちは、最近、後者の視点を取り入れた。それは、マルチン・ルターにゆかりのある反ユダヤ人彫刻を、教会が保存するようラビたちが要求した時である。初期の海外宣教にまつわる記念碑にも、疑問が投げかけられている。昨年、ウィリアムズ・カレッジは、1806年に学生たちが世界宣教への呼びかけをしたことを記念する「干し草の山の記念碑」について、文化的背景を説明するための作業を行った。今日、一部の教授陣は、当時の世界宣教にまつわる「文化的帝国主義」を追認することになるのを恐れている。
日本では、キリシタン迫害の史跡は、その信条のゆえに苦難を受けた人々の信仰、強さ、決意を究極的に指し示すものだ。
「キリスト教弾圧にもかかわらず、日本における宗教的寛容性のおかげで、潜伏しながらの信仰実践は長期にわたり可能となったようだ。」と語るのは、日本人歴史学者の服部英雄氏である。氏はユネスコ遺産推薦を検討するための政府委員会委員長を務めた。「政治権力は、人の心を完全に支配することはできない。これこそまさに、キリシタン関連資産から学べる教訓だ。」
翻訳:立石充子

Annual & Monthly subscriptions available.
- Print & Digital Issues of CT magazine
- Complete access to every article on ChristianityToday.com
- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives
- Member-only special issues
- Learn more
Read These Next
- From the Magazine
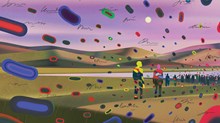 Fifty years ago, the Lausanne Covenant’s solution to rampant division in evangelical ranks wasn’t uniformity.
Fifty years ago, the Lausanne Covenant’s solution to rampant division in evangelical ranks wasn’t uniformity. - Editor's Pick
 French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français
French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français













